卒業生メッセージ(ウェブ版)
「馬が好き!」という思いから
めざしたのは、競走馬の世界
JRA獣医師
日本中央競馬会(JRA) 勤務 藤澤 千尋
馬を知り、競走馬と出会って
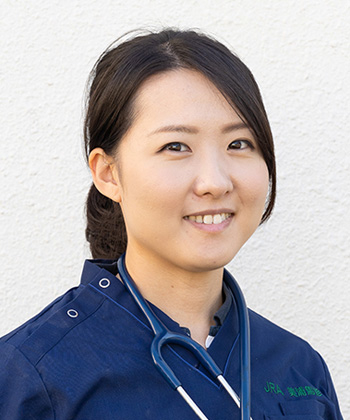 馬のことを身近に感じるようになったきっかけは、麻布大学の「牧場実習」で滞在した乗馬の育成牧場でした。ここで初めて馬と触れ合い、その表情の豊かさに魅了されました。馬は人間とコミュニケーションが取りやすい動物であることもわかり、馬に関すること以外に将来の仕事は考えられなくなりました。
馬のことを身近に感じるようになったきっかけは、麻布大学の「牧場実習」で滞在した乗馬の育成牧場でした。ここで初めて馬と触れ合い、その表情の豊かさに魅了されました。馬は人間とコミュニケーションが取りやすい動物であることもわかり、馬に関すること以外に将来の仕事は考えられなくなりました。
その後、馬についてさらに知るために、乗馬のみならず競走馬の関連施設や生産地などに自ら連絡を取り、見学を試みるように。やがて、多くの人から支えられている競走馬の力になりたいと思うようになりました。
その思いがかなってJRAに入会でき、現在は「美浦トレセン」で獣医師として3年目を迎えています。トレセンとは、トレーニングを積みつつレースに備える競走馬が常時2,000頭ほどいる、いわば"選手村"のような場所。競走馬たちはトレセン内に約100か所ある厩舎のいずれかに所属し、各厩舎の管理は調教師が責任を持って行います。調教師は厩舎の従業員に調教の指示などを出したり、馬主と相談の上でレーススケジュールを決めたりといった役割を担っています。
そして、美浦トレセンにはJRAが運営する診療所があり、私を含めて約15人の獣医師が実働部隊として働いています。私たち獣医師は、日々の調教における万一の事故に備えて監視しながら待機するほか、運動器疾患をはじめとする診療、骨折などに対する手術まで行っています。
多くの思いを乗せて、生を全うするために
 JRAの獣医師にもそれぞれが得意とする領域はありますが、専門ごとの役割分担はありません。一人ひとりの獣医師が皆、同じ内容を同じレベルで診療できることを、基本体制としています。しかし、手術に関しては術者と麻酔管理者で完全に分かれています。入会3年目あたりからその役割が明確になり、私は術者として、手術のメンバーに新たに加わるようになりました。
JRAの獣医師にもそれぞれが得意とする領域はありますが、専門ごとの役割分担はありません。一人ひとりの獣医師が皆、同じ内容を同じレベルで診療できることを、基本体制としています。しかし、手術に関しては術者と麻酔管理者で完全に分かれています。入会3年目あたりからその役割が明確になり、私は術者として、手術のメンバーに新たに加わるようになりました。
一般診療における私が遭遇した症例として、下顎の炎症から口を十分に開けられない馬がいました。調教師をはじめとする厩舎スタッフから「諦めないで、できる限りの治療をしてほしい」という言葉があり、その思いに応えるべく治療に専念しました。幸い症状が改善し、レースでその馬が優勝したことで調教師からお礼の言葉をいただきました。人馬の力になれた喜びとともに、仕事のやりがいをより一層感じるようになりました。
馬一頭が競走馬になるまでの道のりは、決して楽ではない――この事実を知ったのは大学時代でしたが、できるだけ多くの現場に足を運んだことで、身に染みて感じるようになりました。競走馬は生産牧場で生まれ、育成牧場で人に乗られたり調教されたりすることに慣れた後、美浦および栗東のトレセンにある厩舎に入り、ようやく一人前の競走馬としてデビューを果たします。私は生産牧場で種付け(受胎)から1歳になるまでの過程を目の当たりにしましたが、受胎や出産は簡単にはいかないこと、先天性の疾患や育成途中の病気やケガなどによって競走馬になれない馬がいることを知りました。
また、レース中の重度の骨折や心不全で、救命できないケースがあることも知りました。このような状況だからこそ、「競走馬として生を全うさせたい」と強く思っています。
知れば知るほど、視野と可能性が広がる
一頭の馬が無事に競走馬として生きていくためには、生産者や育成者、調教師や装蹄師......実にさまざま人たちの支えが必要であることも、大学在学中に現場で見聞きしました。獣医師にしても、繁殖を手助けする獣医師もいれば、手術を専門的に行う獣医師などもいます。多様な職種を知ったことで、馬の世界のことはもちろん、職業選択に対する視野が広がりました。自主的に動くほど、自らの可能性も広がったと思います。さらには、大学時代に複数の牧場や施設で経験したことは多角的に考えるベースとなり、これからの診療の場面で生かされることが多々あるはずです。
今後も獣医師としてチャレンジを続けたいと思います。競走馬の余生として、いつか馬が飼えたらいいですね。








