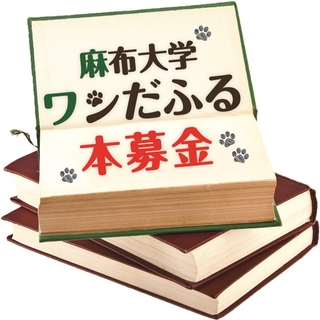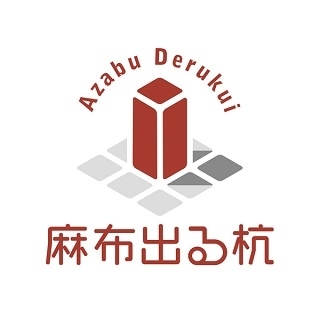【学生インタビューあり】環境科学科学生有志が「ZERO CARBON賞」を受賞


11月18日(土)に青山学院大学で開催された「ZERO CARBON ポスターセッションチャレンジ(主催:相模原市 企画運営:青山学院大学)」で、麻布大学生命・環境科学部環境科学科の3年生・2年生・1年生の有志グループDSSAU(ダッソー)が「ZERO CARBON賞」を受賞しました。
このイベントは、「2050年の脱炭素社会の実現に向けて市⺠や事業者を巻き込んで相模原市が行うべき施策について」をテーマに、大学生がアイデアをポスターと動画にまとめ、意見交換をするイベントです。青山学院大学、桜美林大学、国士舘大学、麻布大学から10チームが参加しました。
麻布大学DSSAUは、「柴刈り⇒ゼロカーボン」をテーマに、公園や里山での柴刈り(焚きつけ用の小木や枯枝を集める作業)にキャンパーや市民が参加し、野外活動や防災教育・環境教育をしながら公園や里山の管理に参画することで、ゼロカーボンである木質バイオマス資源の活用、公園や里山の生態系保全、公園や里山の管理を通して多様な主体の連携と協働(パートナーシップ)と学びが生まれることで、相模原でのSDGsの貢献にも資する提案でした。
リーダーの小嶋雅司くん(3年生)とプレゼンをした遠藤華さん(2年生)のインタビューを紹介します。


Q1.小嶋君、受賞おめでとうございます。このイベントに参加したきっかけを教えてください。
小嶋:相模原市環境審議会の公募委員をしているのですが、同じ審議会委員である環境科学科の大河内先生と髙田先生に参加を勧められました。環境を学んでいるので、良い機会だと思い、前から一緒に活動していたDSSAUの仲間を誘って参加しました。
Q2. みなさんは、元々どんな活動をしていたのですか?
Q3. 今回の提案はどの様に生まれたのですか?
公園や里山には「柴」が放置されています。他方、キャンパーは薪や着火剤を買っています。そこで、多様な主体を「柴刈り」からつなげて、課題を資源に変える「カーボンサイクル」とSDGsの同時解決を考えてみました。
Q4. 遠藤さん、ZERO CARBON賞、おめでとうございます。
Q5. 服装や道具もインパクトがありましたね。
Q6. 今後の活動について教えてください。
遠藤:今回の提案は柴刈りからカーボンサイクルをつなぐことの重点を置きましたが、実際に動かすには情報の共有や発信が必要になります。ここで、GISやデジタルマッピングを活用して、人と人、人と地域をつないでゆく手法を開発し、実装してみたいです。
小嶋:ゼロカーボンやSDGsだけでなく、ウェルビーイングの向上も視野に入れて、柴刈りから活動してゆきます。

<関連情報>
環境科学科の学生が相模原市主催「ZERO CARBONポスターセッションチャレンジ」で発表します