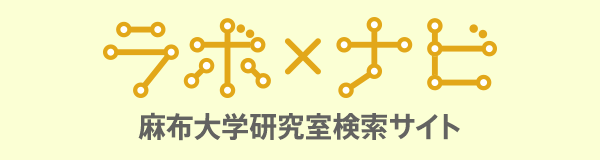研究室一覧
-
- 環境分析学研究室
- 環境中の微量な化学物質を分析・モニタリングし、環境の健康状態を診断する
教授:伊藤 彰英
准教授:中野 和彦
- 研究テーマ
- 河川や土壌、生体中の化学物質の分析・モニタリング
最新の分析装置で、河川や土壌、生体試料に含まれる極微量な化学物質を分析する技術開発や、環境への影響を診断する研究を行っています。
- 研究対象
河川、マイクロプラスチック、土壌、生体中の極微量元素
-
- 水環境学研究室
- 微生物の視点から、生命を支える安全な水の持続的利用を考えよう!
教授:大河内 由美子
- 研究テーマ
- 水環境、健康関連微生物、生物処理
目に見えない水中微生物を対象として、水処理に役立つ機能を調べたり、水環境・水利用における病原微生物の挙動を調べています。
- 研究対象
水環境、水道水、微生物
-
- 環境衛生学研究室
- 環境を保護(まも)り、生命(いのち)を衛(まも)る
教授:関本 征史
講師:落合 真理
- 研究テーマ
- 伝子変異、がん、大気汚染、水質汚染、ヒトや環境への毒性
環境化学物質のヒト疾病発症や環境への悪影響(生態毒性)について、細菌や培養細胞、モデル生物などを用いて調べています。
- 研究対象
環境化学物質、毒性試験、ヒト、ペット、環境生物
-
- 環境生物学研究室
- 身近な生物との持続的かつ適切な共生について一緒に考えよう!
准教授:片平 浩孝
- 研究テーマ
- 外来種問題、希少種保全、害虫管理、都市生態学、水産学一般
家の中に出てくる身近なゴキブリから大自然に暮らす希少種まで、「人間活動との落とし所」をキーワードに幅広く生物の問題を扱っています。
- 研究対象
害虫・害獣駆除、生物資源管理、脊椎動物、無脊椎動物
-
- フィールド科学研究室
- ヒトとその他動植物との関係を、さまざまなフィールドで調べよう!
教授:関本 征史(兼務)
助教:坂西 梓里、新田 梢
- 研究テーマ
- 生物多様性、指標生物、寄生と共生、環境と感染症
自然から都市部のフィールドまで、野生植物や寄生虫を対象にして、生物同士や環境と生物の関係を調べています。
- 研究対象
野生植物、寄生虫、都市自然環境
-
- 地域社会学研究室
- 社会調査を通じて居心地の良いコミュニティを見つけましょう
教授:大倉 健宏(兼務)
- 研究テーマ
- 社会調査法、ペットフレンドリーなコミュニティ、社会疫学調査
動物を間に挟んだ人と人の関係を、地域社会調査を通じて明らかにします。
- 研究対象
地域社会、ドッグパーク、海外調査
-
- 地域環境政策研究室
- 持続可能な地域づくりのための学びと研究、実践を一切合切やってみよう
教授:村山 史世
- 研究テーマ
- 持続可能性、主体的な学び、市民自治、SDGsの自分事化、デジタル・マッピング
持続可能な地域づくりの知識と手法を体験的に学び、自ら創造します。
- 研究対象
里山、公園、デジタルマッピング、ワークショップ、SDGs、法
学部共通
-
- 国際コミュニケーション研究
- ビジネスと学術で生かせる実践英語のトレーニング
教授:伊藤 彰英(兼務)
講師:ジョナサン・リンチ、城山 光子
- 研究テーマ
- 英語教育
ビジネス英語、学術英語、科学英語を教育しています。
- 研究対象
英語
-
- フィールドワーク研究室
- 動物の行動を理解し動物と人との共生を実践する
教授:江口 祐輔
- 研究テーマ
- 野生動物の行動、鳥獣害対策、野生動物と人との共生
動物の行動や心理を理解した上で、動物と人との軋轢を解消する手法を考え、動物と人との共生をめざしています。
- 研究対象
野生動物、外来種、家畜
-
- 教職課程研究室
- 環境・科学を教育の視点で見つめ直そう!
教授:小玉 敏也、福井 智紀
- 研究テーマ
- 環境教育学、ESD論(持続可能な開発のための教育)、理科教育学、科学教育学
理科教育や環境教育に関する教材開発や、社会教育施設における教育活動のあり方を検討しています。
- 研究対象
学校、教材、動物園・水族館
-
- 数理・データサイエンス研究室
- データサイエンスを駆使して新しい価値観を創生するための人材育成
教授:伊藤 彰英(兼務)
准教授:西脇 洋一
- 研究テーマ
- データサイエンス教育
人工知能を中心としたデータサイエンスを学習するためのICT教材開発などを行っています。
- 研究対象
データサイエンス、人工知能、ICT教材
その他、各研究室の詳細は「ラボ×ナビ」をご覧ください。