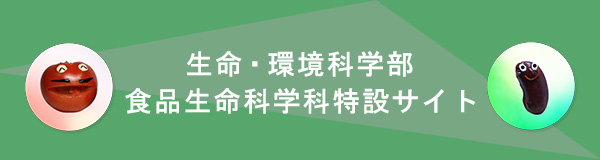教授 村山 史世
生命・環境科学部 環境科学科

- 研究室
- 地域環境政策研究室
- 所属と主な研究内容
- 憲法、法学、環境パートナーシップ、ESD・環境教育、主体的学び(アクティブラーニング)、遊び仕事、国連2030アジェンダ・SDGs、地方自治、空間情報処理・GIS
- 担当科目
- 「法学入門」「日本国憲法」「人権論」「地域コミュニティ論」「環境フィールドスタディ」「インターンシップ」「地球環境科学(分担)」「地球共生論(分担)」
MOVIE
プロフィール
日本大学法学部と日本大学大学院法学研究科で憲法・行政法を学ぶ。日本大学法学研究科博士前期課程修了・同博士後期課程単位取得退学(法学修士)。米国ワシントン州立大学大学院で政治科学を学ぶ(Master of Liberal Arts in Political Science)。早稲田大学比較法研究所助手を経て、1999年より麻布大学環境保健学部講師。2008年より麻布大学生命・環境科学部環境科学科講師。2021年より麻布大学生命・環境科学部環境科学科准教授。2025年より麻布大学生命・環境科学部環境科学科教授。
麻布大学で奉職後は、学生とともに地域での環境活動およびまちづくり・地域づくりの実践に関わりながら環境学習・ESD(持続可能な開発のための教育)を学ぶ。この手法を「師弟同行型PBL(Problem-Based Learning)」と呼んでいる。
「未来の学びと持続可能な発展・開発研究会(みがくSD研)」を環境心理学、環境社会学、環境行政、地方自治、法学、ESD、教育学など多様な専門性と、環境省、県、市の行政経験者や市民団体(NGO)といった多様な経歴をもつメンバーで開催し、「主体的な学びと持続可能性」について、専門分野を「越境」して研究している。現在の主要なテーマは「国連2030アジェンダ・SDGsを自治体計画に取り入れる方策」と「地域連携教育」である。
2008年より環境カウンセラー(市民部門)。海老名市環境審議会委員。座間市市民協働推進会議委員。相模原市都市計画審議会委員。
相模原市緑区の限界集落「青根」の休耕田を復活させた水田を拠点に、生物多様性の把握、環境学習、地域づくりの実践を行う学生・教員・市民の団体「あざおね社中」の会長として活動している。実践活動の実績として以下のようなものがある。
・第28回タカラ・ハーモニストファンド活動助成「カヤネズミ等を指標とした里地里山の生物多様性の調査と自然かんさつ会」500千円獲得(平成25年度)
・全国わがまちCMコンテスト最優秀賞(平成26年度・平成27年度)
・相模原市緑区Short Film Festival We Love 緑区CM部門賞受賞(平成26年度)
・生物多様性アクション大賞2015入賞(平成27年度)
・国連生物多様性の10年日本委員会認定連携事業に認定(平成28年10月)
最近の著作 (researchmapで随時更新)
- 村山史世 「iNaturalistを活用した生き物観察ワークショップの実践 -都市公園で生物多様性を自分事化する-」 日本環境教育学会関東支部年報 No. 19 (2025)
- 村山史世 「レイヤの重なりとして地域を理解する ―GISと地域学習―」 日本環境教育学会関東支部年報 No. 18 (2024)
- 村山史世 「2030アジェンダ・SDGsを自分事化するためのツールの開発 第3報 SDGsグリーンマップ」日本環境教育学会関東支部年報 No. 17 (2023)
-
坂西梓里・村山史世 「SDGsを共通言語とした大学と企業の共創型PBL ―ESD for 2030の一実践―」 日本環境教育学会関東支部年報 No. 16(2022)
- 村山史世 地域のことは地域だけでやらない 相模原 (25) (2021)
-
村山史世・清水玲子・小林久美子・松田剛史・勝浦信幸・石井雅章 「オンラインSDGsワークショップの可能性 ―サイエンスアゴラ2020における実践―」 日本環境教育学会関東支部年報 No.15(2021)
- 村山史世・谷津直生「散乱ごみの実態調査によるアダプト・プログラムの効果測定」麻布大学雑誌 Vol. 31 (2020)
- 村山史世・渡邉菜乃花「2030アジェンダ・SDGsを自分事化するためのツールの開発 第2報 SDGsレンズ 」日本環境教育学会関東支部年報 No.14 (2020)
- 石井雅章・陣内雄次・村山史世・長岡素彦「若者の学びが創出するローカル・ガバナンスの可能性 」関係性の教育学 Vol. 18-1 (2019)
- 村山史世・石井雅章・陣内雄次・高橋朝美・滝口直樹・長岡素彦・村松陸雄「2030アジェンダ・SDGsを理解し、自分事化するためのワークショップの実践―6つの事例と自分事化のフェーズ 」武蔵野大学環境研究所紀要 No.8 (2019)
- 村山史世「現実の課題に基づいた学びとしての PBL、 ESD と共生教育」共生科学 Vol.9 (2018)
- 村山史世「師弟同行型PBLについて -状況的学習と地域共創」関係性の教育学 Vol. 17-1 (2018)
- 村山史世・相場史寛「2030アジェンダ・SDGs を自分事化するためのツールの開発」日本環境教育学会関東支部年報 Vol. 12 (2018)
- 村山史世・滝口直樹「自治体・地域づくりから見た2030アジェンダ・SDGsの可能性についての予備的考察」武蔵野大学環境研究所紀要 Vol. 7 (2018)
- 村山史世「ESDの教材としての自治体計画と2030アジェンダ・SDGs--地域課題を取り扱う主体的な学びのために--」 日本環境教育学会関東支部年報 No.11 (2017)
- 村松陸雄・石井雅章・田中優・長岡素彦・村山史世「3つの実践例から考えるPBLの設計とPBLによる変容」武蔵野大学環境研究所紀要 Vol. 6 (2017)
-
村松陸雄・村山史世「ノンフォーマル教育は大学における持続可能な開発のための教育(ESD)の触媒となるか?」 武蔵野大学環境研究所紀要 No.5 (2016)
-
小玉敏也・村山史世 「実践事例2 地域の多様な教育資源を活かした実践 神奈川県相模原市立青根小学校」 佐藤学・木曽功・多田孝志・諏訪哲郎 編著 『持続可能性の教育-新たなビジョンへ-』(2015) 教育出版
-
村山史世・小此木美咲・小宮菜摘 「ESD 化された環境教育プログラムにおける参加者およびスタッフの変容」 日本環境教育学会関東支部年報 No.9 (2015)
-
村山史世・小宮菜摘 「教育プログラムをESD化するための一手法について」 武蔵野大学環境研究所紀要 No.4 (2015)
-
村山史世 「ESDの実践と地域社会の変容」 日本環境教育学会編『日本の環境教育第2集 環境教育とESD』(2014) 東洋館出版社
-
村山史世 「大学の地域共創と活動の評価 : 学生の環境まちづくりを中心に」 共生科学 vol.3 (2012) 日本共生科学会
-
村山史世 「自治体の環境キャラクター キャラクターはメッセンジャー」 環境会議31号 (2009)
-
村山史世 「第16章 人として根本的なニーズ 基本的人権の原理と限界」 石埼学・笹沼弘志・押久保倫夫編著 『リアル憲法学』(2009) 法律文化社
-
村山史世 「第18章 多忙な憲法の番人 裁判所」 石埼学・笹沼弘志・押久保倫夫編著 『リアル憲法学』(2009) 法律文化社